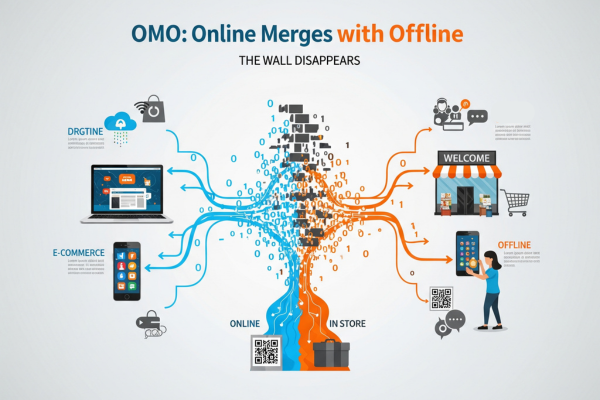リアル店舗 × ECの「再設計」成功事例集|OMOが機能する構造とは
売上は動いてる。でも、なにかが噛み合っていない気がする。
「店舗ではしっかり接客できているのに、ECではなぜか成果が出にくい」
「アプリで便利にはなったけど、“うちらしさ”が伝わっていない気がする」
そんな感覚、心当たりありませんか?
数字はそこそこ動いている。現場も頑張っている。
それでも、「もっとできるはずなのに…」という引っかかりが残る。
もしかしたらそれ、“チャネルごとの最適化”ではなく、“体験全体のつながり”が足りていないサインかもしれません。
今回は、いま注目されている「OMO(Online Merges with Offline)」という考え方を軸に、 “お客さまとの関係性”をどう再構築するか、具体的な実例を交えてお届けします。
お客さまの頭の中に「店舗」や「EC」なんて境界はない
オンラインとオフラインがつながっていて当たり前の時代に
昔は、「オンラインで集客して店舗に呼び込む(O2O)」とか、「どのチャネルでも同じように買える(オムニチャネル)」という考え方が主流でしたよね。
でも今は、もっと一歩進んでいます。

「店舗とECを分けるんじゃなくて、ひとつの“体験”としてデザインする」。
それが「OMO」という考え方です。
だから今、必要なのは“体験”の組み直し
店舗とECのどちらかが主役という時代じゃなくなりました。
大事なのは、お客さまの動きに合わせて、どこで触れてもストレスなく、心地よくつながっていくこと。
そのためには、ただ仕組みを整えるだけじゃ足りないんです。
「体験をどう設計するか?」が問われているんですね。
お客さまの“好き”や“迷い”にちゃんと応えられてる?
モデルケース①|アプリでおすすめ → 店舗で試す → ECで買う
あるファッションブランドでは、アプリがユーザーの好みを学習して、ぴったりの商品をおすすめ。
気になったらアプリから店舗に取り置きして、試着もできる。
そして、後日オンラインで購入、なんて流れもスムーズ。
オンラインもオフラインもひとつの「体験」として設計しているから、どこで買っても“私のため”感がある。
結果として、リピート率もアップしていったそうです。
モデルケース②|接客+デジタルで「今すぐ提案」
別のセレクトショップでは、スタッフがタブレットを持って接客。
「この商品、別のカラーもありますよ」と、その場でEC在庫を見せながら提案できる。
さらに、アプリでおすすめの通知が届いたり、再来店を促すメッセージも。
お客さまの気持ちが冷めないうちに、ちゃんと届ける。
そんな気配りができる構造になっているんですね。
モデルケース③|「在庫がない」は言い訳にならない時代
店舗で「在庫が切れてます」って、ちょっと残念な気持ちになりますよね。
でも、あるブランドではそんな時、スタッフがすぐにタブレットでEC在庫をチェック。
その場で注文できる仕組みがあるから、買う側としてはとても助かります。
「欲しいときに買える」って、実はものすごく大きな価値。
売上を逃さないだけじゃなく、お客さまの満足度もグッと上がります。
モデルケース④|食品スーパーのOMO化
中国の大都市に展開する次世代型スーパーでは、アプリを通じたキャッシュレス決済、30分以内の配送、購入履歴からのおすすめ提案などが導入されています。店内は清潔感があり、イートインスペースで購入した食材をその場で調理してもらえる仕組みもあり、日常に楽しさを添える“場”としての価値が高まっています。
モデルケース⑤|スポーツ用品店のバーチャル試着体験
あるスポーツ用品店では、来店者の顔をスキャンし、バーチャルでウェアの試着ができるモニターを設置。ビッグデータを活用して、顧客の好みに応じたシューズをレコメンドするスマートスクリーンや、ECサイトとの連携によるシームレスな購入体験が可能です。
モデルケース⑥|無人レジと購買データを活かしたOMO店舗
アメリカで展開されている無人レジ型の店舗では、スマホアプリを使って入店し、商品を手に取って店を出るだけで決済が完了。カメラやセンサーによって顧客の購買行動が記録され、データを活用した体験改善が進んでいます。
こうした国内外の事例は、OMOが単なるデジタル施策ではなく、「買いたい・知りたい・楽しみたい」に応える体験設計の延長線上にあることを教えてくれます。
GMOクラウドECなら、やりたいことにちゃんと応えられる
① デザインも、連携も、やりたいことをそのまま形にできる
GMOクラウドECは「ヘッドレス構成」を採用していて、
デザインの自由度も、チャネルとの連携のしやすさも段違い。
- 店頭スタッフのタブレット
- アプリでのレコメンド表示
- 店舗のPOSや基幹システムとの在庫連携
こういった複雑なつなぎ方も、柔軟に対応できるんです。
② API連携と設計力で“変えられるEC”を実現
CRM、MAツール、決済、WMSなどなど。
外部サービスとAPIでスムーズにつながるのはもちろん、「どう連携すれば一番いいか?」を一緒に考えてくれる設計力も魅力です。
OMOを始めたいけど、「どこから手をつけたら…?」という方こそ、ここは頼れるポイント。
③ ロイヤルティやAI活用も、必要なだけ選べる仕組み
「ステージごとにクーポン出したい」
「カゴ落ちのリマインド配信したい」
「AIで“あなたにぴったり”を提案したい」
そんなマーケティング施策も、MAツールとの連携や外部サービスの組み合わせで柔軟に対応できます。
もちろん、3Dセキュアなどのセキュリティ対応は標準搭載で安心。
やりたいことがあっても、今までのECだと「それは難しいですね」と言われていたこと。
GMOクラウドECなら、「一緒にどうやるか考えましょう」が返ってきます。
顧客に響く“心地よさ”は、設計でつくれる
OMOは単なる流行りではなく、「今のお客さまが求めていること」にちゃんと応えるための考え方です。
一度つながったお客さまと、どう継続して関係を深めていくか。
そのカギを握るのが、リアルとデジタルをまたいで“心地よく買える流れ”をつくることなんです。手段を足すのではなく、気持ちよくつながる体験をどうつくるか?
それこそが、これからのECに必要な視点だと私たちは考えています。

試してみたい構想、頭の中で止まっていませんか?
OMOをやりたい気持ちはある。
でも、社内の体制や仕組みを思うと、なんだか腰が引ける。
——そんなふうに立ち止まってしまうケース、たくさん見てきました。
でも実は、OMOって「壮大な改革」ではなく、
今ある強みを活かしながら、少しずつ“つなげていく”ことが出発点なんです。
やりたいことがまだぼんやりしていても構いません。
その輪郭を、いっしょに描いていきましょう。
※関連リンク:「GMOクラウドEC」公式サイト