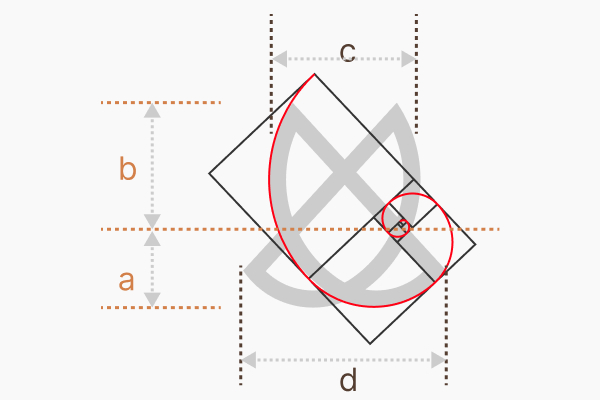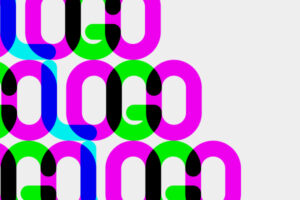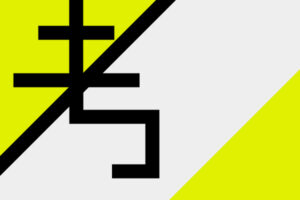「猫っぽい」は偶然じゃない。
その形に、“仕組まれた感覚”を
「もずくとおはぎ」という名前は、聞くだけで印象に残りますよね。
食品の会社?もずく?と、おはぎ?──確かに、そう思われても 不思議ではありません。
実は、この社名、代表・浦川が飼っている2匹の愛猫の名前が由来なのです。
- 落ち着きがあり、理性的な「もずく」
- 本能で動く、好奇心旺盛な「おはぎ」
私たちの事業領域には、IT・Webの分野と、芸術・表現の分野があります。
その中で「もずく」は【左脳=理性的=構想・戦略・分析力】、
「おはぎ」は【右脳=本能的=直感・自由な発想】として、
それぞれのスタンスを象徴する存在になっています。
異なる思考や領域を掛け合わせ、そこにシナジーを生む。
それが社名に込めたコンセプトであり、ロゴもまた、この考え方をかたちに落とし込むことから取り掛かりました。
たまに、ロゴを見て「猫ですか?」と聞かれることがあります。
ちょっと嬉しくなります。
なぜなら、このロゴの狙いはまさにそこ。
“猫に見える”のではなく、“猫っぽく見える”くらいの抽象度を目指していたからです。
感覚から、導き出す構造
「適当にロゴ作ってください」
たまに、そんなふうに軽く言われることがあります。
でも実際には、「この方向だ」と思えるまでに100以上のスケッチを描くことも少なくありません。
関係ない落書きも混じっていますが、それすらも大事なプロセス。
しっくりこないときは、手を動かし続けながら、何を足して、何を引くかを探っていく作業になります。
もずくとおはぎの例にすると、最初に浮かんだのは、「円と円の対比」というアイデアでした。
右脳と左脳──この2つをどうやって図形でどう表現するか?
円を描いては重ね、傾け、ずらしてみる。
左右非対称にしたり、完全な対称を崩してみたり。
そしてその中で、「猫っぽい」シルエットを感じる瞬間を探していく。
最終的には、右脳と左脳のかたちから着想を得た半円を交差させる構造が、イメージ通りの形として残りました。
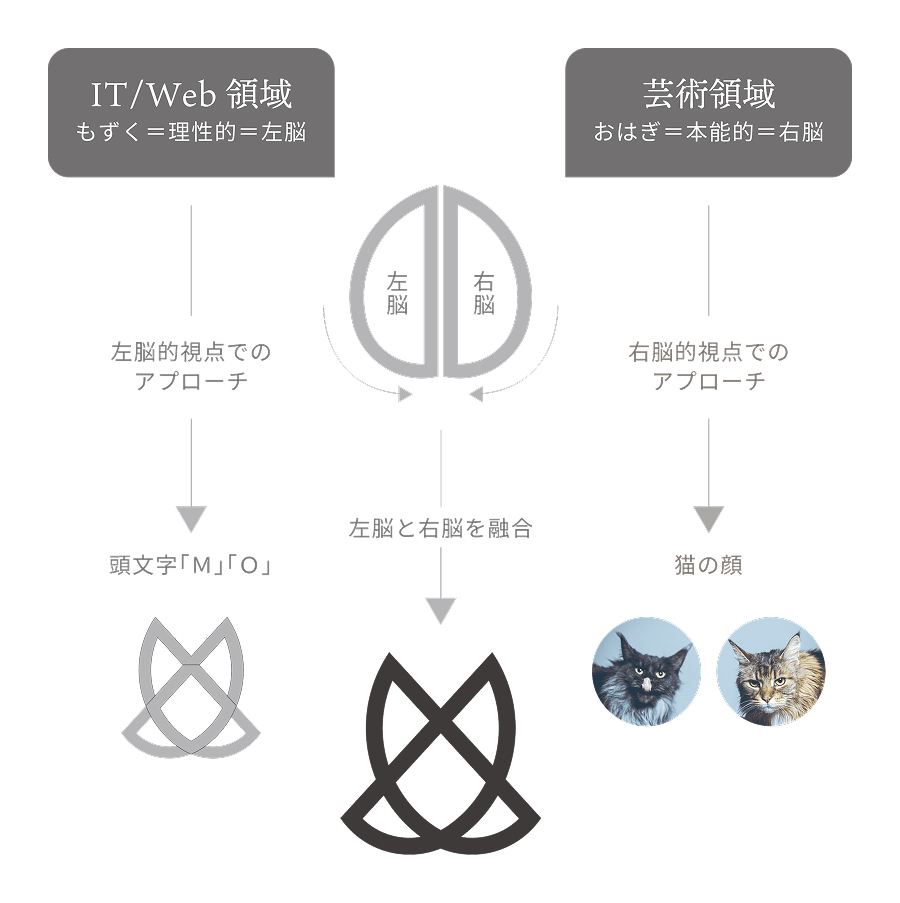
感覚で始まり、思考で整え、構造に落とし込んでいく。
そうしてようやく、「これだ」と言える一案が見えてきます。
感覚を、構造に落とし込む。
形が定まったあとに取り組んだのは、「構造を仕込む」という作業でした。
たとえば、黄金比(1:1.618)や白銀比(1:1.414)をベースに、円の配置、重なり方、耳の角度、余白の取り方まで細かく設計しました。
これは、見たときに「なんか気持ちいい」と思える理由を、偶然ではなく、必然に変えるためのデザインです。
媒体が変わっても、時間が経っても、印象が崩れないように、“感覚”ではじまったものを、“構造”へと着地させ、このロゴの「耐久性」を強化していく作業になります。
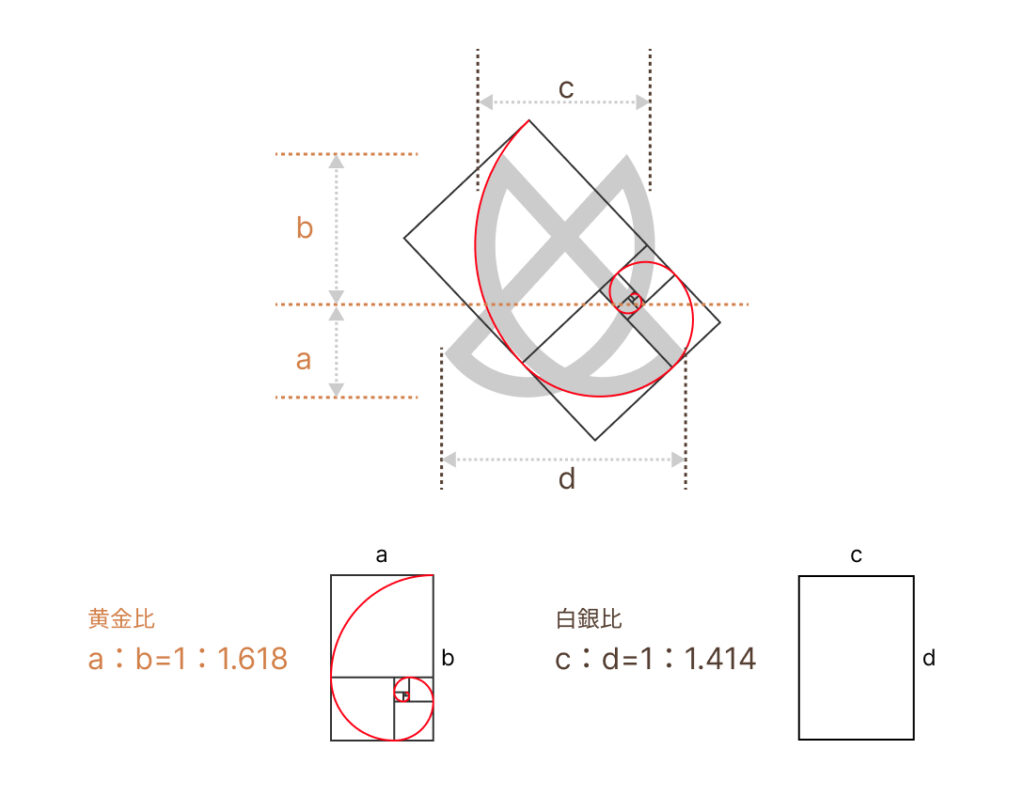
語ることで、ロゴは育っていく。
このロゴをつくるとき、「全員が意味を語れるようにしよう」なんて、言葉にしていたわけじゃありません。
もちろん、そうなることを理想とはしています。
ただ、もずくとおはぎのメンバー5人とも、みんながそれぞれの言葉で、ロゴについて語れます。
猫のこと。名前のこと。図形の意味。感覚と構造の話。
どこかで聞いた説明をなぞるんじゃなくて、ちゃんと自分たちのものとして語っています。
「かわいい」「おしゃれ」も大事。
でもその奥に、“なぜこれなのか”を話せる何かがあること。
それがたぶん、長く残るロゴのかたちなんじゃないかと思っています。
社名であれ、商品であれ、サービスであれ、それに携わる人が、そのロゴについて語れることが、ロゴとして理想形です。
語ることで、自然と愛着が生まれ、伝える熱量が高まり、結果として、ロゴ自体が育っていくものだと思います。
ロゴが育つというのは、ただ印象が定着するということではなく、思考や造形の背景が、チームやプロジェクトの中で浸透し、時間とともに耐久性を増していくことだと思っています。
そのためには、まず気に入ってもらうことが大事ですし、「カッコイイ」「オシャレ」「カワイイ」「好きだ」と思える感覚的な魅力が重要です。
だからこそ、感覚から構造へのプロセスを大切にしています。

ロゴ制作に関するお悩みなどございましたら、お気軽にご相談ください!