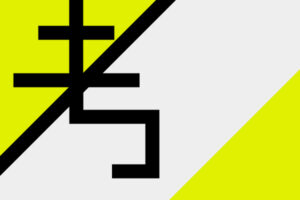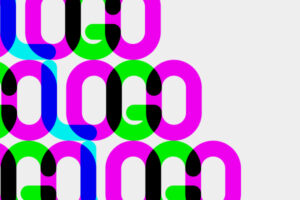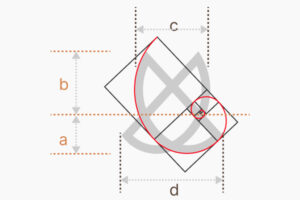“使いやすさ”って、誰の基準?
「これなら迷わないだろう」
「わかりやすく整理したつもり」
——その“つもり”が、誰かの迷いを生むことがあります。
“使いやすさ”とは、いったい何なのか。
そして、それは誰のための基準なのかを、考えていきたいです。
“ユーザー目線”とは?
「ユーザー目線」という言葉を、知らず知らずのうちに使っていませんか?
でも、あらためて考えると、ユーザーってだれなのでしょう。
たとえば——
・“直感的”と言いながら、それが「自分にとってわかりやすいだけ」になっていないか
・関係者間で共有されている背景やルールを、ユーザーも知っている前提で設計していないか
・「説明しなくても伝わる」と思ったものが、本当にそうなっているか
「ユーザー目線」と言いながら、結局は“自分だったら”を前提にしてしまっていることはないでしょうか。
でも、それは本当のユーザーとは違うかもしれません。
ユーザーの目線は、意外とズレて見えていることもあります。
だから毎回、ちょっとだけ立ち止まってみるようにしています。
「親切」より、「邪魔にならない」設計
“わかりやすさ”が、必ずしも“親切”になるとは限りません。
たとえば、操作のたびに表示されるガイドや、すべての機能をずらりと並べたメニュー。
どちらも意図は親切でも、かえって迷いやストレスにつながる場合があります。
大事なのは、使う人が迷わず判断できるように、情報の配置や見せ方を工夫できているかどうかです。
UIを考えるときには、“伝えたいこと”が、“伝わりやすい状態”になっているかを丁寧に見直すことを心がけています。
情報設計は、「正しさ」じゃない
UI/UX設計は、唯一の正解を導く仕事ではありません。
むしろ、“迷わせない”や“引っかかりのなさ”をどうつくるかが大切です。
だからといって、ただ情報を削ればいいわけでもなく、
・伝えるべきことを見極めて、何を足すか・引くかを判断する
・ユーザーが“知らなくていいこと”まで含めて、構造を整える
・言葉に頼りすぎず、流れや配置で意図を伝える
必要なのは、「正しさ」より「適切さ」。
ときには、意図を伝えることより、意図に気づかせないほうがスムーズなこともあります。
具体例を挙げると、以前リニューアルをさせていただいた、KAICOさんのサイトでは、
ファーストビューに、矢印や「スクロールしてください」のようなガイドは入れていません。
それでも多くの人は迷うことなく、自然に読み進めていくと思います。

視線の流れや余白設計など、細かな工夫によってスクロールしたくなる構造を意識したUIで、
「行動を促す」ことよりも「迷わせない」を選んだUIと言えるかもしれません。
UIを考えるとき、作り手の意図をそのまま届けるよりも、
ユーザーの“なんとなくの行動”に寄り添う方がうまくいくことがあります。
意図を説明するよりも、気づかれずに伝わる方が心地よいです。
そんな視点で見直すことは、設計に欠かせないと考えています。
立ち返るべき視点とは?
「これならきっと伝わる」——そう思いながら設計したものが、まったく伝わらなかった経験はありませんか?
そんなときに立ち返りたいのは、「本当にこれは使いやすいのか?」というユーザーの視点。
・どこで止まったのか
・どこで戸惑ったのか
・なぜそこで戻ったのか
使い手の行動には、設計者の見落とした違和感が表れています。
それに気づけるかどうかで、UI/UXの質は大きく変わっていきます。
「わかりやすさ」や「親切さ」は、押しつけるものではありません。
気づかせること、迷わせないこと。
UI/UXに正解はなくても、頼りにすべき軸はあって、
それはいつだって、使う人の側にあります。
サイト制作に関するお悩みなどございましたら、お気軽にご相談ください!