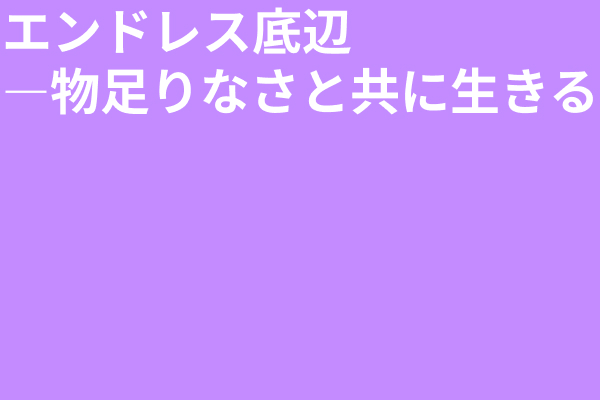エンドレス底辺──物足りなさと共に生きる
全ては物足りなさから始まる
ずっと「自分には、まだ何かが足りない」と思い続けている。
経営も、芸術も、言語も、戦略も。
一定の水準に達した次の瞬間、明確なもうひとつ上の層が浮かび上がる。到達したと思ったその場こそ、次のピラミッドの底辺だったと気づくとき、自分がまだまだ小さく、未熟で、未完成であることに打ちのめされるほどの絶望。
でも、なぜだろう。この物足りなさにこそ、自分の根源的な創造欲が刺激されている。未完成であることを恥じるのではなく、それこそが人間としての尊厳の証ではないかと思えてくる。
「まだ、やれることがある」「もっと、深く届けられる」
この感覚が、自分を前に進める推進力となっている。もはや足りていないことを否定するのはナンセンス。むしろ、それがあるからこそ脳がフル回転し、人と出会い、新たな問いが生まれる。
物足りなさは欠乏ではない。むしろ、それは『まだ何かを生み出せる』という確かな手応えなのだ。
そして何より、この飢えが自分のクリエイティビティの原泉。完成形なんて要らない。今この瞬間も、底辺に立つ自分が一番強いと思える。
ほどほどで満足してもいい時代に、なぜ抗うのか
現代は「ほどほどでいい」「無理せず生きよう」も主流のひとつだ。燃え尽き症候群も、メンタルケアも、働きすぎのリスクも、誰もがある程度理解している。バランスを取りながら生きることは、悪いことじゃない。むしろ、命を守る上でとても大切なことだ。
だけど、同時にこうも思う。
その“ほどほど”は、本当に自分が望んだバランスなのか?
それとも、周囲が決めた「快適さ」の中に自分を閉じ込めていないか?
たとえば、「まあまあできる」「そこそこ評価される」領域にとどまってしまえば、居心地はいいかもしれない。でも、そこにとどまり続けることが内なる欲求の萎縮を生む。
誰に求められなくても、自分の内側から湧き出す熱。それを持っている人が放つ光は、見ていてすぐに分かる。
“ほどほどでいい”と言い聞かせたとき、あなたはその光を殺していないだろうか。
疲れたなら、休めばいい。だけど、満足したふりをして“まだ燃えている自分”を無視するのは違う。
飢えたり、渇いたり。その中から何かを生み出せるなら、あなたはまだ生きている。
個人が停滞すると、組織が停滞する
個人の「もうこれでいいや」は、組織の停滞に直結する。
仕事に慣れ、安定し、ある程度の成果も出ている。その心地よさの中で、次第に“とがり”が削れて丸くなっていく。対話も形骸化し、ミーティングの言葉に意図が乗らなくなり、提案が消化試合のようになっていく。
組織は、構成員のエネルギーの総和で動く。だからこそ、たったひとりの「ま、いっか」が、他の誰かの「まぁいっか」を呼び、気づけばチーム全体が停滞していく。
進もうとする側にとっては足手まといなのだ。
経営層やリーダーが「もう十分やった」と感じてしまった瞬間だとさらに重たい。そこから先にあるのは、緩やかな死だ。
そんな場面をたくさん目の当たりにしてきた。
自分が止まれば、未来が動かなくなる。
自分の熱が消えれば、周囲の温度が下がる。
だから、物足りなさを抱えている人間は、それだけで組織に火を灯す存在だと思う。「もう一段階、先に行ける気がする」
そう言える人がチームにいるかどうかが、未来の可能性を左右する。
エンドレス底辺を心地よく感じながら
では、どんなスタンスでいたらいいのだろうか。
私は、こう定義している。
「常に、次のピラミッドの底辺に立ち続ける」こと。
いくら経験を積み、成果を上げ、実績を積んでも、どこかで自分を“再び初心者に戻す”勇気を持つ。
新しい世界に触れ、新しい問いに立ち、新しい技術に怯え、新しい美意識に嫉妬する。それに対峙して、自分の殻を壊していく。
エンドレス底辺とは、成長が無限であるという構えではない。 成長の余白を常に自分の中に確保し続ける姿勢だ。
未熟であることを恐れない。むしろ、未熟であることに安らぎさえ覚える。それは、「まだ先がある」という幸福でもあるから。
底辺から見える世界こそが、実は一番の絶景。
一番自由で、一番可能性に満ちている。
人生はまだ半分(以上)も、在る。